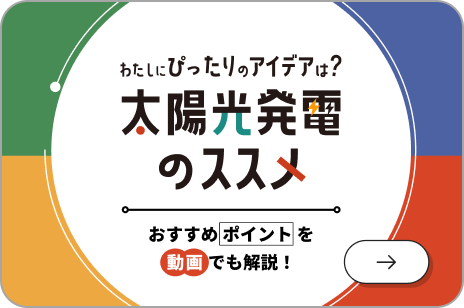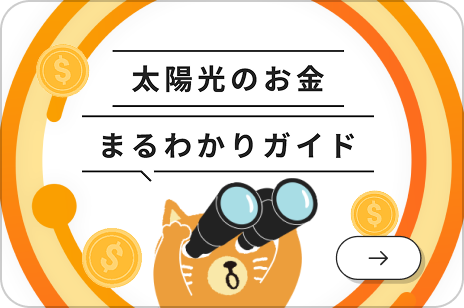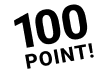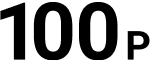コラム

公開日:2025.7.31

volume 02
家庭用蓄電池とは?
メリット・デメリットや
種類、選び方を解説
1 家庭用蓄電池とは?
1.1. 家庭用蓄電池の仕組み
- 太陽光パネルが太陽の光を受けて直流の電気を発電する
- 発電した電気をパワーコンディショナで直流から交流に変換する
- 分電盤を通じて交流の電気を家庭内の各部屋や家電製品に振り分ける
- 余った電気を再び直流に変換し、蓄電池に貯める
- 蓄電池にためた電気をパワーコンディショナで直流から交流に変換し、家庭内に供給する
- ※経済産業省「家庭用蓄電池(蓄電システム)について DRready勉強会」
1.2. 覚えておきたい!
家庭用蓄電池にまつわる用語
| 用語 | 意味/概要 |
|---|---|
| 蓄電池 | 充電によって電気を蓄え、繰り返し使用できる電池。乾電池のような使い切りタイプを「一次電池」と呼ぶのに対し、蓄電池のように繰り返し使えるタイプを「二次電池」と呼ぶ。 |
| パワーコンディショナ (以下パワコン) |
太陽光発電などの設備で発電された電流を直流から交流に変換する装置。電気を変換するだけの機器で、単体では電気を利用できない。 |
| リチウム イオン電池 |
現在の家庭用蓄電池の主流である充電式蓄電池。正極と負極のリチウムが酸化・還元することで電気エネルギーを生成する。 |
| 容量(kWh)・ 出力(kW) |
|
| 全負荷型・ 特定負荷型 |
|
- ※参考:資源エネルギー庁「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~「蓄電池」は次世代エネルギーシステムの鍵」
- ※参考:環境省「公共施設への再エネ導入 第一歩を踏み出す自治体の皆様へ PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の手引き」
- ※参考:経済産業省「参考資料(蓄電池)」
- ※参考:経済産業省「リチウムイオン蓄電池の規制対象化に関するFAQ」
- ※参考:一般社団法人 太陽光発電協会「kW(キロワット)とkWh(キロワットアワー)の違いは何ですか?(よくあるご質問)」
2 家庭用蓄電池の種類と特徴
2.1. 単機能型
- ※経済産業省「家庭用蓄電池(蓄電システム)について DRready勉強会」
2.2. ハイブリッド型
- ※経済産業省「家庭用蓄電池(蓄電システム)について DRready勉強会」
2.3. 多機能型
- ※経済産業省「家庭用蓄電池(蓄電システム)について DRready勉強会」
3 家庭用蓄電池のメリット4つ
3.1. 電気料金を節約しやすい
3.2. 余剰電力を活用できる
- (注)最新の情報は経済産業省などの公式ウェブサイトをご確認ください。
- ※参考:資源エネルギー庁「FIT・FIP制度」
3.3. 災害時の非常用電源として
活用できる
- (注)
- ・停電時に使用できる機器はあらかじめ専用配線に接続しておく必要があります。専用配線は、平常時・停電時ともに定格出力(自立)まで使えます。
- ・停電時に蓄電池に電気が貯まっている前提です。
3.4. 地球環境に優しい
4
家庭用蓄電池の
デメリット4つ
4.2. 長く使う工夫が欠かせない
4.3. 設置する場所が必要になる
4.4. メリットを活かしきれない
可能性がある
- (注)ご利用には会員登録が必要です。
蓄電池を中部電力ミライズに相談してみませんか?
ご相談もお気軽に!
蓄電池をさらに詳しく!
5
家庭用蓄電池を選ぶ際に
確認すべきポイント4つ
5.1. 容量と出力は適切か?
5.2. 設置スペースと設置条件は
問題ないか?
- 直射日光があたらない
- 熱がこもらない
- 高温多湿でない
- 寒冷地でない
- 積雪地域でない
- 塩害地域でない
5.3. 保証期間とアフターサービスは
充分か?
5.4. 活用できる補助金はないか?
- ※参考:「DR家庭用蓄電池事業」
- ※参考:名古屋市「令和7年度 住宅等の脱炭素化促進補助(暮らしの情報)」
蓄電池を中部電力ミライズに相談してみませんか?
ご相談もお気軽に!
蓄電池をさらに詳しく!
6 家庭用蓄電池の最新事情
- ※参考:経済産業省「2024年度 定置用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ」
7 まとめ
- (注)各自治体と協定を締結した事業者が太陽光発電や蓄電池の購入希望者を募り、機器の一括仕入れで価格の引き下げを実現する制度。制度の有無については、お住まいの自治体のウェブサイトをご確認ください。
蓄電池を
中部電力ミライズに
相談してみませんか?