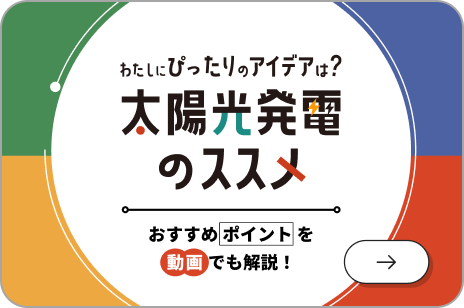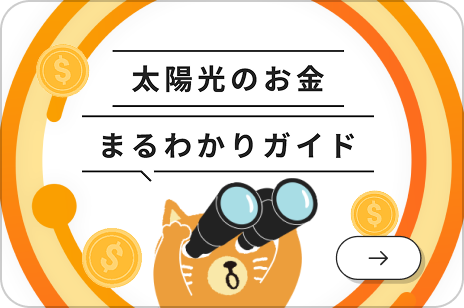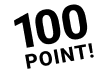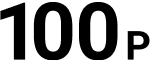コラム

公開日:2025.11.6

volume 09
【2025年】
太陽光蓄電池の補助金を
活用しよう!
制度概要と
申請手順を解説
1 太陽光発電と蓄電池を導入する場合の費用相場
- 新築住宅:28.6万円/kW
- 既築住宅:32.6万円/kW
- (注)2023年度における家庭用蓄電システムの導入費用内訳は、設備費:15〜20万円/kWh、工事費:約2万円/kWh。
- ※参考:資源エネルギー庁「太陽光発電について」
- ※参考:経済産業省「2024年度 定置用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ」
2 2025年も太陽光発電と蓄電池の補助金はある?
| 補助金名 | 対象 | 提供元 | 対象機器 |
|---|---|---|---|
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 新築・既築(リフォーム) | 国(国土交通省) | 太陽光(ZEH基準)、蓄電池(リフォーム対象工事に含まれる場合) |
| DR補助金 | 既築(需給調整契約のある住宅・施設(注)) | 国(環境省) | 蓄電池 |
| 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 | 新築・既築 | 自治体(東京都) | 太陽光、蓄電池 |
| 犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 既築 | 自治体(愛知県犬山市) | 太陽光、蓄電池 |
| 住宅等の脱炭素化促進補助 | 新築・既築 | 自治体(愛知県名古屋市) | 太陽光、蓄電池 |
| 豊田市エコファミリー支援補助金 | 新築・既築 | 自治体(愛知県豊田市) | 太陽光、蓄電池 |
- (注)需給調整契約のある住宅・施設:電力会社やアグリゲーターと契約し、電気が余る時間に蓄電池へ充電したり、電気が不足する時間に放電したりして電力需給の調整に協力する住宅や施設のこと
- ※参考:環境省「2025年度 エネルギー対策特別会計における補助・委託等事業」
3 ①子育てグリーン住宅支援事業
3.1. 新築の場合
3.1.1. 補助対象住宅と補助額
| 補助対象住宅 | 1戸あたりの補助額 | 住宅の解体工事が必要な場合の補助額の加算額 |
|---|---|---|
| GX志向型住宅 | 160万円/戸 | なし |
| 長期優良住宅 | 80万円/戸 | 20万円/戸 |
| ZEH水準住宅 | 40万円/戸 |
- ※参考:国土交通省・環境省「子育てグリーン住宅支援事業 事業概要 新築について」
3.1.2. 補助対象者
| 補助対象事業 | 補助対象者 |
|---|---|
| 注文住宅の新築 | 住宅の建築主 |
| 新築分譲住宅の購入 | 住宅の購入者 |
| 賃貸住宅の新築 | 住宅の建築主かつ賃貸オーナー |
| 補助対象者 | 定義 |
|---|---|
| 子育て世帯 | 申請時点で18歳未満の子を有する世帯 |
| 若者夫婦世帯 | 申請時点で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯 |
- ※参考:国土交通省・環境省「子育てグリーン住宅支援事業 事業概要 新築について」
3.2. リフォームの場合
3.2.2. 補助額と上限額
| タイプ | 補助の条件 | 上限額 |
|---|---|---|
| Sタイプ | 必須工事1~3のすべてのカテゴリーを実施 | 上限60万円/戸 |
| Aタイプ | 必須工事1~3のうち、いずれか2つのカテゴリーを実施 | 上限40万円/戸 |
- ※参考:国土交通省・環境省「子育てグリーン住宅支援事業 事業概要 リフォームについて」
3.3. 交付申請期間
4 ②DR補助金
- ※参考:DR家庭用蓄電池事業「事業概要」
4.1. 補助額
4.2. 補助の条件
- 日本国内に事業所を持つ法人または個人事業主であること(居住者含む)
- 補助対象設備(蓄電池)の所有者であること(リース型でも一定条件で申請可)
- 事業の継続性が認められる経理管理体制を有していること(個人を除く)
- DR契約の締結またはDRメニューへの加入をおこなうこと
- 申請・報告などSII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)とのやりとりに必要なシステムの利用や連絡体制が整っていること
- 経済産業省等の実地検査や調査に協力できること
4.3. 公募期間
5 ③東京都
| 項目 | 助成金なし | 助成金あり(分割還元) |
|---|---|---|
| 月々の料金等 (リース料・割引額など) |
約36,850円 | 約24,725円 |
| 総額 | 約4,422,000円 | 約2,967,000円 |
| 助成額 | ― | 約1,455,000円 |
- 想定設備構成:太陽光モジュール(4.10kW)、パワコン(4.00kW)、蓄電池(6.50kWh)
太陽光発電を中部電力ミライズに相談してみませんか?
ご相談もお気軽に!
太陽光発電をさらに詳しく!
- ※参考:東京都地球温暖化防止活動推進センター「中部電力ミライズ 助成金還元時の料金比較表」
6 ④各自治体による太陽光発電と蓄電池の補助金
6.1. 愛知県犬山市
- ※参考:愛知県犬山市「犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金」
6.2. 愛知県名古屋市
- 新築の戸建住宅に設置する場合:1万円/1kW(上限9.99kW)
- 築10年以内の戸建住宅に設置する場合:2万円/1kW(上限9.99kW)
- 築10年超の戸建住宅に設置する場合:3万円/1kW(上限9.99kW)
- 共同住宅に設置する場合:2万5千円/1kW(上限9.99kW)
- ※参考:名古屋市「令和7年度 住宅等の脱炭素化促進補助」
6.3. 愛知県豊田市
| 補助対象設備 | 補助率 | 補助金上限額 |
|---|---|---|
| スマートハウス (太陽光・HEMS・蓄電池またはV2H) |
定額 | 21万円/1件 |
| スマート・ゼロハウス | 定額 | 26万円/1件 |
| 蓄電池またはV2H (蓄電容量7.5kWh未満) |
蓄電容量1kWhあたり1万円 | 15万円/1件 |
| 蓄電池またはV2H (蓄電容量7.5kWh以上) |
定額 | |
| 燃料電池 | 設置費用の5% (設置工事費を含む) |
5万円/1件 |
- ※参考:豊田市「豊田市エコファミリー支援補助金」
7 各自治体の補助金は国の補助金と併用できる?
8 まとめ
太陽光発電を
中部電力ミライズに
相談してみませんか?